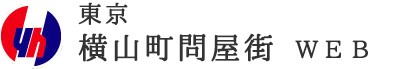浜野製作所 代表取締役会長CEO 浜野 慶一氏
本社兼工場が消失。大きな転機を迎えた
墨田区は全国でも有数の工場集積地
東京都墨田区は近代軽工業発祥の地といっていい地域です。鐘ヶ淵紡績(現カネボウ)、小林富次郎商店(現ライオン)、精工舎(現SEIKO)、長瀬商店(現花王)、札幌麦酒東京工場(現アサヒビール)、資生堂石鹸(現資生堂)など、今や世界的に知られる企業が墨田区で創業しました。
高度経済成長期には墨田区内に9703の工場がありました。それが時代の変遷と共にその数は減少し、現在は最盛期の1/5程度の1500ほどですが、東京都では大田区に次いで第2位、全国でも有数の工場集積地です。工場が最も多かった時代と2025(令和7)年の現在でも1社の企業規模はほとんど変わっていません。全体の80%は従業員5人以下、さらに半分は従業員3人以下の工場です。中小企業というより小規模零細、家族系規模の工場が大半を占めています。そういう地域です。
浜野製作所は1978(昭和53)年に創業し、今期で48期目を迎える町工場です。父が創業し、私は2代目です。従業員が現在60名、パートやアルバイト、他の企業からの出向を含めても70名という小さな規模の工場です。当初は金型を製作していましたが、日本が活況を呈していた時代に金型にとどまらず、その金型を使った部品加工も手がけるようになりました。家電製品に使われる大量生産の部品を製作して家電メーカーに納めていました。
技術と取り組みに高い評価
私が社長に就任したのは1993(平成5)年です。取り巻く環境や時代背景が大きく変わっていきました。特に量産の部品加工はどんどん海外の生産拠点に移っていきました。単価も厳しくなっていきました。2000(平成12)年には近隣の火災の類焼によって本社と工場が全焼してしまうという不運に見舞われました。
ここが大きな転機となりました。大量生産の手法のプレスの金型をあえて戦略的に残しながら、金型を使わない金型レスの少量多品種の部品加工、業界では「精密板金」と呼ばれる分野を始めました。 そして最近はロボット開発や装置開発を含めてさまざまな分野で技術開発を進めています。自主的に物づくりを核としながらもその周辺サービスも手がけるようになり、経済産業省や中小企業庁、東京都などの行政機関などにサービスを提供しています。
そうした活動が評価されて、03(平成15)年に墨田区より優良工場である「『フレッシュゆめ工場』モデル工場」の認定を受けました。05(平成17)年に「すみだがげんきになるものづくり企業大賞」、07(平成19)年に「じょうとうIT経営大賞」の優秀賞を受賞しました。14(平成26)年に経済産業省の「平成25年度おもてなし経営企業」に選定されました。そのほかにも数多くの賞を受賞していますが、中でも最も印象的だったのが、経済産業省の「第7回ものづくり日本大賞」で経済産業大臣賞を受賞したことです。これは日本一というもので、その時の2位が京セラ、3位がトヨタ自動車でした。2社とも日本のトップ企業です。彼らを抑えて、私たちの技術と取り組みが高く評価されたと、社員と喜びを分かち合いました。
視点を変えて、デメリットをメリットへと転換
物づくりのイノベーションを支える
弊社が考えている方向性は次の三つです。
①物づくりの情報の上流からのコミットメント(地域性)
②下請け体質からの脱却(方向性)
③ネットワークの活用(中小企業での限界)
物づくりのフェーズは「相談」→「設計・開発」→「試作・検討」→「量産加工」→「組込・組立・検証」という工程です。どの業界、業種でもできれば量産加工のところで仕事がしたい。大手企業に近いところで安定した、継続した量産の仕事は売り上げが見込めます。経営者であれば当たり前のことです。
でも量産加工のフェーズはどんどん海外生産にシフトしていく。単価も下がってくる。私たちは東京です。土地代も高いし、人件費も高い。住宅地に工場があるので、騒音や振動の問題もあります。夜は機械を動かすことができません。同じ機械を使っても地方や海外の工場の1/4か1/5くらいしか稼働させることはできません。もしかしたら日本でいちばん物づくりに適していない地域で物づくりをしているかもしれません。地方や海外の工場と同じことをしていても到底、勝ち目はありません。
一見してデメリットに見えるこの東京という地域が、物づくりの考え方や仕組み、枠組み、視野を変えることによって最大のメリットとなるような物づくりを発信できるのではないだろうか。私たちは本社2階に「ガレージ・スミダ」を立ち上げました。物づくりのイノベーションを支える開発拠点で、スタートアップや大企業の新規事業開発の支援を行っています。これは高度人材が集まる「都市型・先進物づくり」への挑戦でもあります。下請け仕事はもちろん胸を張ってやるべきですが、やはり自らが行動していくことで下請け体質から脱却していくことが大事だと思っています。
我々は小さな会社です。1社でできることには限界があります。企業規模を超えたネットワークの活用に取り組んでいます。設計開発では大企業やベンチャー、大学、研究機関などと協業しています。ブリヂストンや富士通、東北大学や東京工業大学などと研究開発を進めています。各社から出向という形で研究開発を行っています。
こうした連携によって常に先端技術の開発に取り組むことができるようになり、高度な人材が集まるようになりました。中には「社会を変えることができるのは浜野製作所しかない」と一流企業から転職してきた技術者もいました。昔、求人を出しても一人の応募もありませんでしたが、今では大学や高専などの優秀な人材を採用することができます。
常に挑戦する気持ちを持ち続ける
企業や研究機関との連携の一方で、地域連携に取り組んでいるのも弊社の特徴です。墨田区の工場が減少したとはいえ、今でも残っている工場には存在価値があります。この技術をなくしてはいけない。サプライチェーンが崩れていく中で、末端まで仕事が回らないという状況でした。
13年前に立ち上げたのがオープンファクトリー「スミファ」です。工場を開放し、見学やワークショップなどを開いています。最初は地元の人たちに来ていただいていましたが、今は区外、都外、海外からも来ていただくようになりました。墨田の文化にも触れてほしいと、商店街連合会や国際美術館だとか、新日本フィルハーモニー交響楽団、地元の大学や小学校のPTAなど、今までは縦でしかつながっていなかったものにスミファというツールで横串を刺していこうと考えています。
さまざまな取り組みを通して、弊社は大きく変化してきました。町工場の特性と技術を磨いていくことで時代の先端を走ることができます。大手にも負けないポテンシャルを持つこともできる。これからも常に挑戦する気持ちを持ち続けていきたいと思います。■